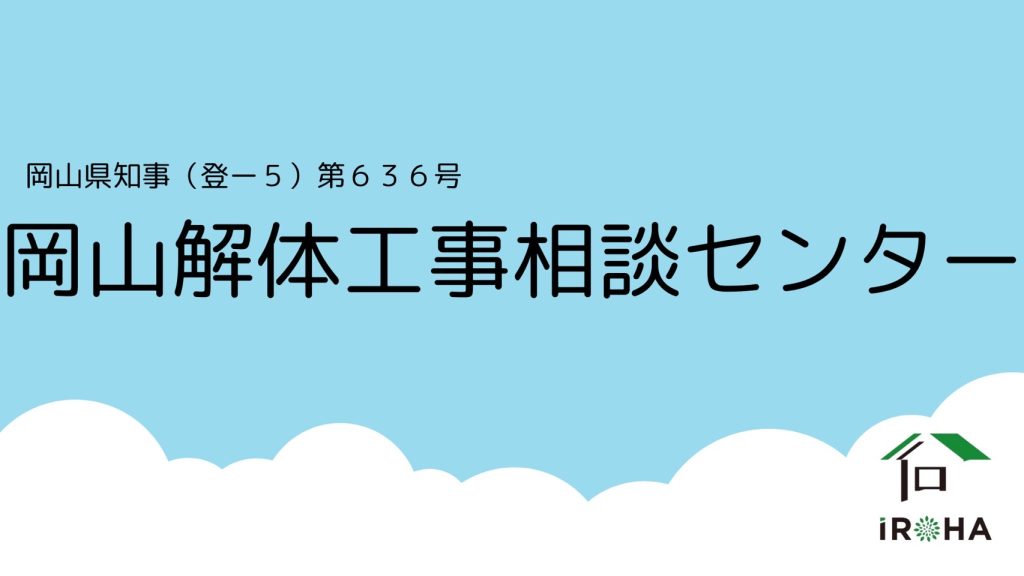
こんにちは、岡山県の解体・土地整備専門店【株式会社いろは】です。
今日は、解体工事前に行うアスベスト調査のアスベストについて解説していきます!!
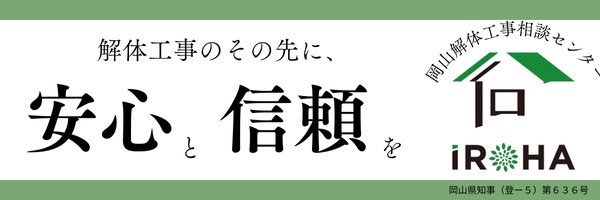
【解体工事とアスベスト問題への関心の高まり】
解体工事が増える中、
「アスベストって何?」 「本当に危険なの?」 「うちの建物は大丈夫?」などといったアスベストに対する不安や疑問の声も多く聞かれます。
古い建物にお住まいの方、リノベーションを検討されている方、あるいは事業主として建物の管理に関わる方にとって、アスベストは決して無視できない重要な問題です。
しかし「どこから手をつけていいのかわか分からない」 「専門用語が多くて理解しにくい」と感じていませんか?
ご安心ください。
この記事では、アスベストに関する基本的な知識から、具体的な除去・封じ込めといった対策、知っておくべき情報を綱羅的に解説します。
アスベスト問題は、知っているか知らないかで、ご自身やご家族、あるいは従業員の健康と安全を大きく左右する可能性があります。
呆然とした不安を解消し、適切な知識と対策を身につけることで、安心して暮らせる・働ける環境を守りましょう。
この徹底解説を読めば、アスベストに関する疑問や不安が解消され、具体的な次のステップが見えてくるはずです。
ぜひ最後までお読みください。
【アスベストとは?基礎知識からリスクまで】
アスベスト(石綿)という言葉を聞いたことはありますか?
おそらく、多くの人が耳にしたことはあるでしょう。
しかし、それが具体的にどのようなもので、なぜ危険視されているのか、その全てを理解している人は少ないかもしれません。
1・アスベスト(石綿)とは?

アスベストは、天然に存在する繊維状の鉱物で、その語源はギリシャ語で「不滅のもの」を意味する「asbestos」に由来します。
その名の通り、非常に優れた特性を持つことから、かつては「奇跡の鉱物」とも呼ばれていました。
【アスベストの主な特徴】
- 耐熱性・耐火性:高温に強く、燃えにくい。
- 断熱性・保温性:熱を伝えにくい。
- 電気絶縁性:電気をほとんど通さない。
- 耐薬品性:酸やアルカリに強い。
- 摩擦体制:摩擦に強い。
- 引っ張り強度:非常に丈夫。
- 加工のしやすさ:繊維状で柔軟性があり、様々な形に加工できる。
これらの優れた特性から、アスベストは1970年代から1980年代にかけて、建材、自動車部品、電気製品など、実に3000種類以上の製品に利用されてきました。
特に日本では、高度経済成長期の建築ラッシュにおいて、安価で高性能な建材として大量に使用されました。
【アスベストの種類】
アスベストには大きく分けて以下の6種類がありますが、特に日本ではクリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)が多く使われていました。
- クリソタイル(白石綿)
- アモサイト(茶石綿)
- クロシドライト(青石綿)
- トレモライト
- アクチノライト
- アンソフィライト
2・なぜ危険なんのか?アスベストの健康リスク
アスベストが「奇跡の鉱物」から「危険な鉱物」へと認識が変わったのは、その健康被害が明らかになってきてからです。
アスベストの繊維は非常に細かく、空気中に飛散すると、吸い込んだとしても目に見えません。
この目に見えないアスベスト繊維が、私たちの健康に深刻な影響を及ぼすのです。
【アスベストが原因となる主な健康被害】
アスベストによる健康被害は、吸い込んだ量や期間、そして個人の感受性によって異なりますが、潜伏期間が非常に長い(10~50年以上)という特徴があります。
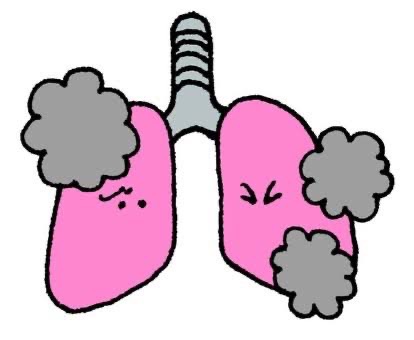
- 石綿肺(じん肺の一種):肺が線維化する病気で、肺機能が低下し、咳や痰、息切れなどの症状が現れます。重症化すると呼吸困難に陥ることもあります。
- 肺がん:アスベストは発がん性物質であり、肺がんのリスクを高めます。喫煙との相乗効果も指摘されています。
- 悪性中皮種:肺や胃、心臓などを覆う膜(中皮)に発生するガンで、非常に悪性度が高く、治療が難しいとされています。アスベスト曝露との関連性が極めて強い病気です。
- 良性石綿胸水:肺を覆う胸膜に水がたまる病気で、アスベスト曝露によって引き起こされることがあります。
- びまん性胸膜肥厚:胸膜が厚くなり、肺の膨らみが悪くなる病気です。
これらの病気は、アスベスト繊維が肺の奥深くまで入り込み、炎症や細胞の異常を引き起こすことで発症すると考えられています。
3・アスベストのリスクが高い状況とは?
アスベストが危険なのは、その繊維が空気中に飛散し、それを吸い込むことによって健康被害が生じるからです。
そのため、アスベストが含まれている建材などが損傷したり、解体・改修作業が行われたりする際に、アスベスト繊維が飛散しやすくなります。
【特にリスクが高い状況】
- アスベスト含有建材の劣化・損傷:老朽化した建物や、地震などの災害によって建材が破損した場合、アスベスト繊維が飛散する可能性があります。
- 建物の解体・改修工事:アスベスト含有建材が使用されている建物の解体や改修工事を行う際、適切な措置が取られていないと、大量のアスベスト繊維が飛散する危険性があります。
- DIYでの改修作業:一般の人が、アスベストが含まれている可能性のある建材を知らずに切断したり、穴を開けたりするなどの作業を行うと、アス散布のリスクがあります。
- 特定のアスベスト関連産業での労働:過去にアスベスト製品の製造や、アスベスト含有建材の施工に携わっていた労働者は、特に高濃度の曝露を受けていた可能性があります。
4・アスベスト対策の現状と今後の課題
アスベストの健康被害が明らかになって以来、世界各国でアスベストの使用が規制されてきました。
日本では、2004年にアスベストの製造・輸入・使用が原則禁止され、2006年には全面禁止となりました。
【現在の主なアスベスト対策】
- 使用禁止:新たなアスベスト製品の製造・使用は全面的に禁止されています。
【既存建築物への対策】
- 調査義務:一定規模以上の建築物の解体・改修工事を行う際には、事前にアスベストの有無を調査することが義務付けられています。
- 除去・封じ込め・囲い込み:アスベストが確認された場合、飛散のリスクに応じて、専門業者による除去、封じ込め(飛散防止剤の塗布など)、囲い込み(アスベストを覆い隠す)などの対策が実施されます。
- 作業基準の強化:アスベスト除去作業における作業員の安全確保や、飛散防止のための厳格な基準が設けられています。
【健康管理】
- 過去にアスベストに曝露した可能性のある人に対する健康診断や相談窓口の設置が行われています。
【情報公開】
- アスベストに関する正確な情報提供や、相談体制の準備が進められています。
【今後の課題】
- 老朽化建築物の増加:高度経済成長期に建てられたアスベスト含有建築物の老朽化が進んでおり、今後ますます解体・改修工事が増加することが予想されます。これに伴い、アスベスト飛散のリスクも高まる可能性があります。
- アスベスト含有建材の把握:全ての既存建築物におけるアスベストの使用状況を正確に把握することは困難であり、潜在的なリスクが残っている可能性があります。
- 不法投棄対策:アスベスト含有廃棄物の不法投棄を防ぐための適切な処理体制の確立が重要です。
- 健康被害への支援:長期的な潜伏期間を持つアスベスト関連疾患の患者に対する継続的な支援が求められます。
5・私たちができること
一般の私たちにとって、日常生活の中でアスベストに曝露するリスクは低くなっていますが、古い建物に住んでいたり、解体工事現場近くを通ったりする際には、以下の点に注意することが大切です。
- 古い建物の改修や解体を行う際は専門家に相談する:ご自宅や所有する建物にアスベストが使用されているか不明な場合は、自己判断せずに専門の業者に調査を依頼しましょう。
- 解体工事現場に近づかない:アスベスト除去作業が行われている可能性のある工事現場には、むやみに近づかないようにしましょう。
- アスベストに関する情報を正しく理解する:国の機関や地方自治体などが提供する正確な情報を入手し、冷静に対応することが重要です。
【まとめ】
アスベストは、かつては便利で安価な素材として重宝されましたが、その繊維がもたらす深刻な健康被害が明らかになってからは、使用が厳しく制限されています。
しかし、既存の建物にはまだまだアスベストが残されており、その対策は、喫緊の課題です。
アスベストに関する正しい知識を持ち、適切な行動をとることで、私たち自身の健康と安全を守り、次世代にクリーンな環境を残していくことが求められます。

解体工事・土地の整地に関するお見積もりやご相談はいつでも無料です!!
少しでも土地をうまく活用したいとお考えの方は、ぜひ一度【株式会社いろは】にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
あなたのお悩みをぜひ一緒に解決していきましょう!!
